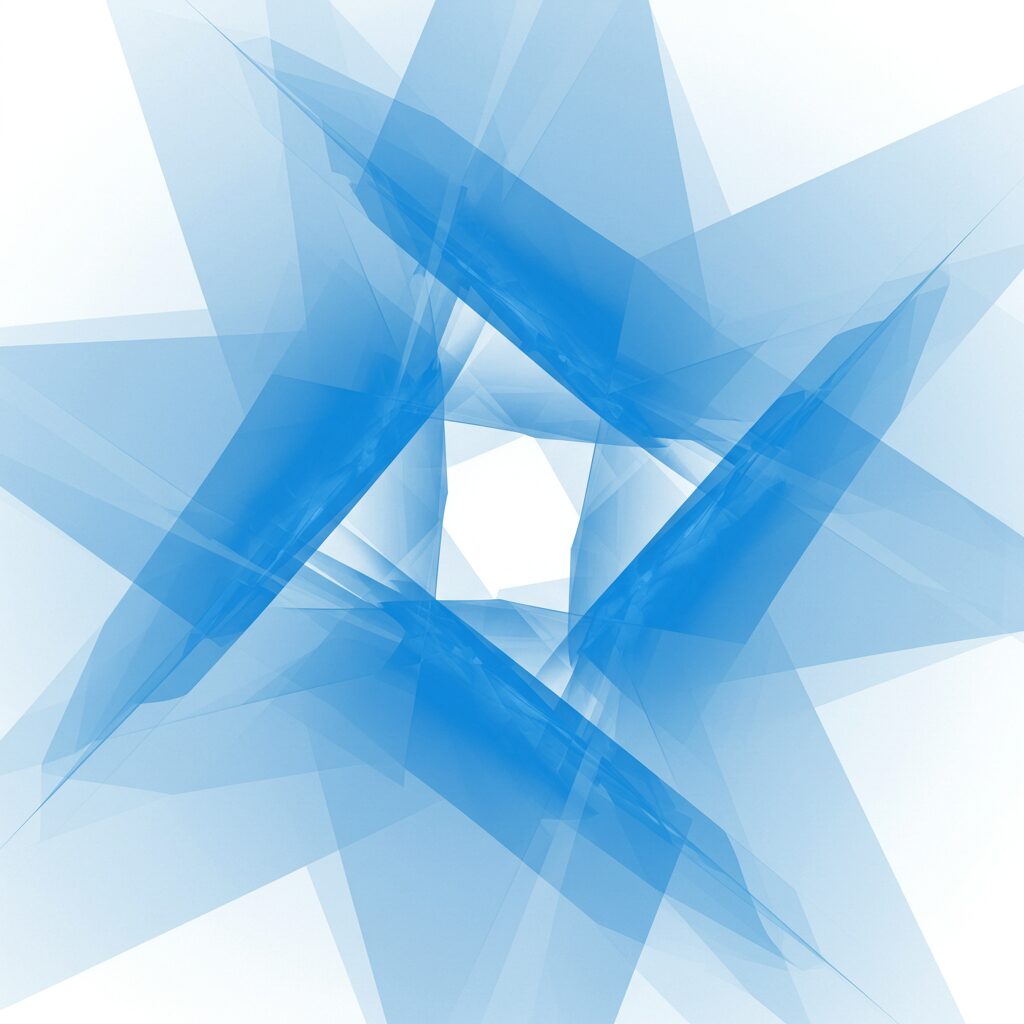- Q退職代行で行政書士に依頼するメリットは何ですか?
- A
①圧倒的なコストパフォーマンス
行政書士は書類作成料金のみなので、一般的な退職代行にくらべても格安です。
②適度なプレッシャーを会社に与えられます。
行政書士が書いた内容証明なら会社に適度なプレッシャーが与えられます。
弁護士からの内容証明は弁護士名で送るので、強いプレッシャーで会社が身構えてしまいがちですが、行政書士の内容証明は依頼者名で送ります。
でも、読めば専門家の介入が分かるので会社は無視できにくくなります。③行政書士法に基づいた合法な仕事です。
行政書士の仕事は、国から許可されていますので問題になることはありません。
- Q未払い賃金がある場合はどうしたらいいですか?
- A
内容証明郵便で支払い請求ができます。また、その請求によって消滅時効が半年間停止できます。(行政書士にできるのはここまで)
退職時に未払い賃金が残っている場合、その請求権は残りますが、残念ながら三年の消滅時効にかかるため、一日ごとに請求できる金額が減ってしまいます。
このような状況で、行政書士がどのようにサポートできるか、そしてその後の対応についてご説明します。■行政書士にできること:時効の停止
弁護士資格がないと未払い賃金の交渉はできませんが、行政書士は内容証明郵便を作成し、送付することで未払い賃金の消滅時効を一時的に停止させることができます。
内容証明郵便で支払いを請求することにより、時効は半年間停止します。
これにより、未払い賃金の請求権が消滅するまでの時間を確保することができます。■その後の対応について
最近では、大手弁護士事務所が初期費用ゼロ円の完全成功報酬制で未払い賃金の請求代理事業を開始しています。
行政書士が内容証明郵便で時効を停止させた後、その後の対応についてじっくり考える十分な時間があります。
この期間に、弁護士への依頼を含め、ご自身にとって最適な方法を検討することが可能です。
- Q契約前でもいろいろ相談できますか?
- A
はい、ご契約前の無料相談も行っています。
まず、行政書士は書類作成に関する法律相談なら合法的に行えることをご承知ください(一般退職代行は法律相談ができません)。
公式LINEやメールであれば、費用は一切かかりません。お電話でのご相談も可能ですが、通話料はお客様のご負担となります。
また、行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、ご相談内容の秘密は厳守いたします。どうぞご安心ください。
もちろん、書類作成に進まなければ料金はいただきません。
- Q退職時に年次有給休暇は使えますか?
- A
はい、問題なく使用できますし、行政書士なら合法的に請求できます。
年次有給休暇は労働基準法で保障された権利なので、労働者が申請すれば会社は拒否できません。
行政書士なら内容証明で有給を請求できますので、会社が認めないと言ったら、労働基準法違反で労働基準監督署に申告する時の証拠になります。
- Q離職票などの退職時書類を会社が渡してくれない場合は?
- A
退職証明書を使用して、各書類を所管する役所を通じて入手します。
退職時書類は次のステップの手続きに必要な書類なので、退職しているのに会社が手続しないままでは役所が困ります。
そこで、退職した証拠として退職証明書を持参して、各役所に出向いて相談すれば役所が救済してくれます。
- Q前職調査(リファレンスチェック)の心配はありませんか?
- A
行政書士は、書類を代書しただけなので、問題になることはありません。