退職代行は「弱者ビジネス」なのか? 私が考えるその解答
先日、YouTubeで退職代行をテーマにした討論番組を視聴しました。若手経営者たちが肯定派と否定派に分かれ、「バックレればいい」という過激な意見から、「ブラック企業には有効な手段だ」「一度使った人はまた使う」など、様々な意見が飛び交い、非常に興味深かったです。
しかし、番組全体を通して感じたのは、多くの出演者が退職代行を「弱者からお金を得るビジネス」と捉えているのではないか、ということでした。ある方が「年商60億規模のスモールビジネス」と表現していたのが、それを象徴しているように思います。
でも、私の退職代行に対する認識は、まったく異なります。
退職代行は「退職時の法務サービス」である
「退職代行」というネーミング(個人的には、とても秀逸だと思います)がついていますが、これは言ってしまえば、退職に際しての法務サービスの一つに過ぎないと私は考えています。
少し話は逸れますが、行政書士が行っている「相続ビジネス」を例に挙げてみましょう。長年、相続は税理士や弁護士の専門領域と考えられていました。しかし、行政書士の金森重樹氏が、相続税が発生しない相続においては空白地帯であることに着目し、新たな市場を開拓しました。つまり、そこに潜在的な需要が存在していたのです。
退職代行も、これと似ているのではないでしょうか。
2万円程度の需要に気づかなかった専門家たち
実は、2万円程度の価格帯で退職を代行してほしいという需要は、以前から存在していたのです。残念ながら、内容証明という強力な手段を持っていたにもかかわらず、行政書士はこの需要に気づきませんでした。
そして、この需要に目をつけ、いち早くビジネスとして始めたのが、無資格業者だったというわけです。
つまり、退職代行は、後から生まれた「弱者ビジネス」なのではなく、最初から潜在的な需要が存在していたのです。だから、使いたい人は使えばいいし、使いたくなければ使わなければいい。そこに「良い」「悪い」といった価値判断を挟む必要はないと私は考えます。
無資格業者のリスクと利用者の注意点
もちろん、無資格業者が開拓した市場であったため、非弁行為などのリスクを内在してしまったという側面はあります。しかし、退職代行を利用する側は、その点を十分に理解し、依頼する業者を慎重に選ぶことで、そのリスクを回避することが可能です。
退職代行は、現代の働き方において、多様なニーズに応える一つの選択肢として確立されつつあります。皆さんは、退職代行についてどうお考えでしょうか?
HOME PAGE→ホーム

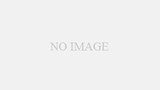
最近のコメント
コメントなし